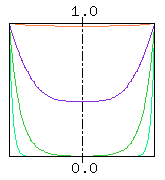
1図 直径 1 mm の軟銅線の表皮効果
円筒導体に流れる電流は直流なら導体断面に一様に分布しますが、 周波数の増加と共に導体表面に集中し、 内部の電流密度が減る現象は「表皮効果」(skin effect)として、 よく知られています。(注1)
例えば、直径 1 mm の軟銅線について、 周波数 10kHz, 100kHZ, 1MHz, 10MHz に対する、 導体断面の電流密度を計算すると、 1図のようになります。
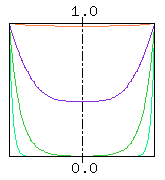
1図 直径 1 mm の軟銅線の表皮効果
1図の x 軸は導体中心からの距離(中央が導体中心、両端が導体表面)、 y 軸は (内部の電流密度/導体表面の電流密度) です。
赤、紫、緑、薄緑の線は、 それぞれ、10kHz, 100kHZ, 1MHz, 10MHz に対する導体断面の電流密度ですが、 導体中心の電流密度は、10kHz で外周部の 98%、 100kHz では 41%、1MHz では 0.4% と減り、 10MHz になると 0.00000006% にしかすぎません。
表皮効果の結果として、導体の実効断面積が減少し、交流抵抗が増加しますから、 コイル巻線では周波数の上昇と共に導体損失が増え、 「Q」(Quality factor - 品質)が低下します。
この対策として、古くから、中波ラジオのバーアンテナのコイルとか、 中間周波トランス等の巻線として使われてきたのが「リッツ線」(Litz wire)で、 これは、 絶縁された複数の細い導体素線を集めて撚合わせたものです。
そこで、 このリッツ線のアイデアを「オーディオケーブル」に活用しようという人々が たくさん居て、 2図のようなことを考えました。
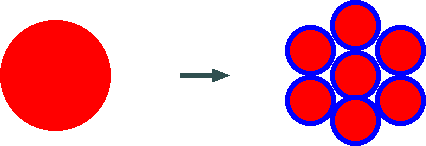
2図 単線導体を複数の絶縁導体に分割する (赤色は導体、青色は絶縁体)
つまり、 1 本の単線導体を導体断面積が同じになるように、 複数の絶縁導体に分割するのです。 例えば、7 本に分ければ、2図のようになりますが、 「分割を増やせば、より表皮効果の少ないケーブルが作れるであろう。 A 社が 19 本なら、当社は 30 本、それも抜かれたら、さらに 1 本増やして ..」 というのが、この種の商品を考える人々の作戦です。
かくて、リッツ線を採用したオーディオケーブルが、たくさん生まれてきましたが、 果たして、この作戦は正しいでしょうか?
これが今回の問題です。
Ir / Ia = I0(sqrt(j)*k*r) / I0(sqrt(j)*k*a) ここに Ir = 半径 r (m) に於ける電流密度 (A/m^2) Ia = 導体外周に於ける電流密度 (A/m^2) a = 導体半径 (m) j = sqrt(-1) k = sqrt(ω*μ*σ) ω = 角速度 (rad/s) = 2*π*f π = 3.14159265.. f = 周波数 (Hz) μ = 透磁率 (H/m) σ = 導電率 (S/m) I0(z) = 第1種0次の変形ベッセル関数 I1(z) = 第1種1次の変形ベッセル関数
ワイヤの表皮効果に関する最初の数学的議論は、 1873 年の現代電磁気学の創始者 Maxwell で、 その後 1884 - 1887 年に Maxwell の理論面の後継者となった、 創意にあふれた天才 Heaviside が大きな貢献をして、 1884 - 1885 年の Poynting へと理論面の発展が続きますが、 実験的な検証は 1886 年の Hughes が最初で、 実用レベルの工学的数値計算については、 無限平板の表皮効果が 1886 年の Lord Rayleigh、 円筒導体については、 1889 年の Lord Kelvin による ber-bei 関数による計算が最初になります。 その後、Maxwell の実験面の後継者である Hertz や J.J.Thomson の仕事が続きますが、 「skin-effect」の用語を最初に使ったのは、 1891 年の J.Swinburne だったようです。 この後、H.B.Dwight や A.E.Kennelly を始めとする、 多くの優秀な理論家や技術者による挑戦が、最近に至るまで続くことになります。
なお、Litz Wire の語源はドイツ語の「Litzendraht」(編組線)だそうです。
平林 浩一, (C) 2003