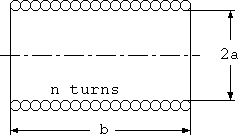
1図 ソレノイド・コイル
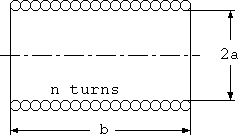
1図 ソレノイド・コイル
電線の中に「マグネット・ワイヤ」(magnet wire)という領域があって、電磁石や コイルの材料として使われますが、その最も簡単な用途が1図のソレノイド・コイル (solenoidal coil)で、コイルの場合、導体を密着させて巻くのが普通ですから、 導体上に薄くて丈夫な皮膜が施してあり、これがマグネットワイヤの本質的な構造 になります。
このコイルの高周波に於ける抵抗とインダクタンスは、コイルの長さがコイルの 半径より大きいという条件で、下記のように近似できることが知られています。
Rhf = 2*π*a/b*n^2*R1 (1) L = μ0*π*a^2*n^2/(b + 0.9*a) (2) ここに Rhf = 高周波抵抗 (Ohm) L = インダクタンス (H) π = 3.14159265.. a = コイルの半径 (m) b = コイルの長さ (m) n = コイルの巻数 (turn) R1 = sqrt(π*f*μ/σ) f = 周波数 (Hz) μ = 導体の透磁率 (H/m) μ0 = 空気の透磁率 (H/m) σ = 導電率 (S/m)R1 は「表面抵抗」(surface registivity)とか「固有抵抗」(intrinsic resistance) と呼ばれる導体固有の指標で、これは、高周波電流が無限平板に流れるとき、 その表面の電圧降下を基準にした実効抵抗です。材料の特性だけで決まるもので、 幾何学的寸法と無関係であることに注意してください。板厚がいくらであろうと、 表皮効果により、電流のほとんどが導体材料の導電率、透磁率、周波数で決まる 特定な深さ以内にしか存在しないためです。
無限に幅が広い板というのは不自然という印象を受ける方がおられるかもしれませ んが、円筒とか円柱表面は本質的に無限平板(円周方向にいくら進んでも縁に達しない!) ですし、電磁波の波長の尺度で見た滑らかな導体表面の一部とか、極めてありふれた 基本的な構造なのです。
さて、このケースでは、高周波電流は表皮効果によって素線表面にしか存在できない うえに、近接効果によって隣の素線に近い部分の電流密度が小さくなりますから、 この2つの原因によって、コイルの内表面と外表面に電流が集中します。
このため、巻き付けピッチに比べて、導体径を少し細くすることで近接効果を 減らすと、コイルの内表面と外表面だけでなく、導体間の隙間にも電流が流れる ようになって、導体径の減少による直流抵抗の増加を上回る交流抵抗の減少が 得られます。むろん、導体径を極端に細くすると直流抵抗の増加も極端に大きく なって、元も子もなくなるわけですから、 最適値が存在することは明らかで、子供のとき、短波ラジオのコイルを巻いた ことのある方でしたら、素線間に隙間ができるように疎巻きしたことを思い出される かもしれません。
ところで、コイルの目的は磁気エネルギの蓄積ですから、リアクタンスと抵抗の比、
Q = ω*L/Rhf (3)でその品質(Quality Factor)を評価するのが普通で、これはまた、
Q = 2*π*蓄積されるエネルギ / 1サイクル毎に消費されるエネルギになっています。
銅やアルミのような非磁性導体によるコイルなら、前期の結果から、次式のように なります。
Q = a/d/(1 + 0.9*a/b) (3)
ここに
d = sqrt(2/(ω*μ*σ))
Q = コイルの Q(quality)
= コイルで消費される電力/コイルに蓄積される電力
d は「侵入の深さ」(skin depth)と呼ばれ、表皮効果の影響を判断するときのよい
目安になりますし、表皮効果に関連する数式の見通しをよくするのに役立ちます。
さて、このコイルと他の回路との干渉を防ぐためコイルをシールドすることはよく 行われますが、ここでは2図のような円筒状のシールドに入れるとします。
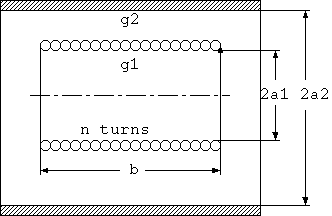
2図 円筒シールド内に置かれたソレノイド・コイル
すると、 電流はコイルの導体層の内側と外側に加えて、シールドの内側にも流れますから、 エネルギ損失は導体内部だけでなく、シールド内部にも発生します。
かくて、コイルの実効抵抗はシールドの影響も受けることになりますが、(1) 式の 「Rhf」はシールドのない場合と比べて増えるでしょうか、同じでしょうか、それ とも減るでしょうか。これが今回の問題です。
平林 浩一, (C) 2000